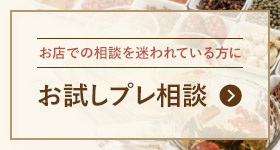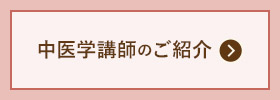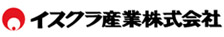今月は、日本橋店に毎週月曜日ご相談されている劉文昭先生にインタビューしました。いつも明るく元気な先生のあれこれをみなさまにご紹介します。
1983 年北京中医薬大学医学部を卒業し、1990 年には中国中医科学院大学院を卒業しました。
中国中医科学院大学院では2、3 年目に、附属の広安門病院循環内科で、老中医と西洋医と一緒に臨床で多くの患者さんを診て学んできました。
朝から晩まで勉強しました。1990 年から7 年間は、広安門病院循環内科の助教授として勤務していました。
質問その2) たしか、日本の大学にもいらしたとか?
1997 年、早稲田大学心理学部に客員研究員として呼ばれました。
このときが日本初来日です。
早稲田の心理学部では、東洋医学の人間科学についての研究もしていて、当時“ 中医学による気質分類”というテーマで論文も書きました。(ヒューマンサイエンスMay2004Vol.16)
体質をチェックして中成薬を使う内容もあります。
質問その3) 今年で来日15 年目になりますね。今、先生がお持ちになっている日本の印象は?
まず、日本人は真面目で優しくとても正直、何事に対しても頑張る人が多いと思いました。
これは、薬局へいらっしゃるお客様からも、薬局の先生方からも感じられることです。
あと、中国では、他人に対してはっきり物事を言うタイプの人が多かったのですが、日本人は謙遜する人が多いですね。
そのため、ストレスを溜めやすい方が多い様に感じます。
私のご相談では、どんな症状のお客様にも必ず、ストレスにより滞った気をスムーズにする理気剤や血液の流れを良くする活血剤を少量でもご服用していただいています。
また、日本はきれい。北京と比べて雨が多く、湿度も高いことがきれいな理由の一つではないかと思い感動しました。
気になることは、日本人は薄着の人が男性も女性も多いこと。
容姿はきれいですが、冷え性の女性が中国よりも多いですね。
特に、若い女性のお血(子宮筋腫、子宮内膜症など)、高齢者の高血圧やむくみなどの原因の一部には、根本に冷えが関わっている人がとても多いと思います。
中国人は冷えの対策として、生姜や胡椒、唐辛子などをよく料理に取り入れます。
質問その4) 劉先生がお好きな故郷・中国の食べ物はなんですか?
もちろん餃子!あと、豚の足の腿の部分を醤油で煮たもの(醤肘子)も大好きです。
ちなみに日本食ではお寿司、お刺身がNo1です!!
質問その5) 最後に一言。皆さんに何かアドバイスがありましたらお願いします。
イスクラに入社してから、中医学の理論だけではなくもっと深い真髄の部分も、多くの薬局の先生方に広めていきたい、勉強して欲しいと思うようになりました。
中国では、何か体に違和感があれば漢方薬を飲みます。
皆様も、病気になる前に何かありましたら早めにご来店ください。
専門は循環内科ですが、婦人科、皮膚科での臨床経験もございます。
“ 未病先防”“ 治未病”です。皆様いっしょにがんばりましょう!
いつも明るい劉先生。
“ 一緒に頑張りましょう”と励ましのお声をかけてくださるのでとても安心してご自分のお体と向き合える気がします。
皆さん、体調のことでお悩みでしたらぜひご相談くださいね!折原



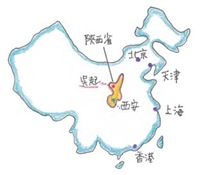

 呉起県は、毛沢東ら紅軍一行が多くの苦難を乗り越えて、
呉起県は、毛沢東ら紅軍一行が多くの苦難を乗り越えて、