こんにちは、櫻井です。
カゼ・インフルエンザ、はやってますね。
そこでカゼ対策について少し書きたいと思います。
「風邪には葛根湯!」とお考えの方も多いと思いますが、
葛根湯は「ぞくぞくする寒気がある、首や肩のこわばりがある」場合のカゼに有効な漢方薬です。熱や喉の痛みが気になる場合はほかのお薬が適しています。
中医学でカゼは自然界の邪気である風邪(ふうじゃ)が身体に入り込んだ事が原因と考えられています。そして、風邪は単独ではなく、他の邪気を連れて体内に入ってくると考えられています。それぞれが特徴的な症状発症させるので、カゼにはタイプがあるという考え方になります。それぞれのカゼのタイプでは症状も違うので、対処法も、使われる薬も変わってきます。
熱邪のかぜ
・発熱やのどの痛みに注意
「熱」のかぜは、急な発熱、身体が熱っぽい、のどが痛い、鼻水や痰が黄色く粘りがあるといった症状が特徴です。インフルエンザもこのタイプに当たります。
まずは身体の熱を冷まして炎症を鎮めることが大切です。
主な症状
・発熱 ・顔が赤い ・口の渇き ・喉の痛み ・鼻水や痰が黄色く粘りがある
食の養生
涼性の食材で熱を冷ましましょう
・ミントティー ・菊花茶 ・ごぼう ・蓮根 ・くず湯
おすすめレシピ
蓮根湯
すりおろした蓮根(1cm厚さ程度)、うすく切った金柑(2枚)、氷砂糖(1個)をカップに入れ、お湯を注いでかき混ぜます。
良くつかわれるのは…
・天津感冒片(てんしんかんぼうへん) ・涼解楽(りょうかいらく) ・板藍根(ばらんこん)
燥邪のかぜ 
・長引く咳は乾燥のサイン
なかなか咳が止まらない、痰が絡む、といった症状は「燥邪」が入り込んだかぜ。長引いた時に良く見られるタイプで、乾燥した「肺」を潤すことがポイントです。
マスクや加湿器等を使い、乾燥を防ぐ工夫も心がけましょう。
主な症状
・咳 ・痰が絡む ・胸が重苦しい ・口が渇く ・皮膚の乾燥 ・便秘気味
食の養生
身体に潤いを与える食材を
・梨 ・枇杷 ・はちみつ ・杏仁豆腐 ・銀杏 ・大根 ・百合根
おすすめレシピ
百合根粥
おかゆを作り、とろみが出てきたら百合根を入れて少し煮込みます。
味付けは塩味であっさりと。
良くつかわれるのは…
・麦門冬湯(ばくもんどうとう) ・潤肺糖漿(じゅんぱいとうしょう) ・百潤露(ひゃくじゅんろ) ・その他百合根含有食品
寒邪のかぜ
・ぞくぞくと悪寒がするかぜの初期
かぜの初期で強い悪寒や頭痛、節々の痛み、水っぽい鼻水といった症状が特徴です。このタイプのかぜは、身体をしっかり温めることが大切。暖かい服装を心がけることはもちろん、食事や入浴などで身体を伸から温めましょう。
主な症状
・悪寒 ・頭痛 ・節々の痛み ・鼻づまり ・鼻水が水っぽい ・顔が青白い ・汗をかかない
食の養生
身体を温める温性の食材を
・生姜 ・ネギ ・ニンニク ・シナモン ・紅茶 ・三つ葉
おすすめレシピ
生姜湯
すりおろした生姜(5g)、黒砂糖(小さじ1杯)、片栗粉(小さじ1)、
水(適量)を鍋で沸騰させれば出来上がり。
ぽかぽか鍋
白菜、大根、ねぎ、鶏肉、生姜をたっぷり煮込んだら、
最後に三つ葉を添えて。ポン酢などお好みの味でいただきます。
良くつかわれるのは…
・葛根湯(かっこんとう) ・小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
湿邪のかぜ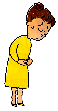
・吐き気や食欲不振などの胃腸障害が特徴
「湿邪」が身体に入り込んだかぜは、胃の痛みやむかつき、食欲不振、下痢といった胃腸障害が特徴です。
体内の「湿(余分な水分)」を取り除きながら、胃腸の働きを整えるよう心がけましょう。
主な症状
・胃のむかつき ・胃の痛み ・食欲不振 ・嘔吐 ・腹痛 ・下痢
食の養生
香りのよい食材で胃の症状を緩和しましょう
・しそ ・生姜 ・みょうが ・チンピ(みかんの皮を干したもの) ・梅干し
おすすめレシピ
しそ湯
しその葉(5g・乾燥したものでも可)とチンピ*(3g)を細かく切って茶袋に入れ、水から煮出します。*乾燥したみかんの皮
良くつかわれるのは…
・勝湿顆粒(しょうしつかりゅう) ・香蘇散(こうそさん)
まずは日頃の予防で“かぜに負けない身体づくりを心がけましょう。それでも罹ってしまったらかぜのタイプに応じた早い対応で、長引かないようにしましょう。
外から帰ったらうがい![]() 手洗い
手洗い をお忘れなく。
症状や体質は一人一人異なりますので、薬局・薬店でよくご相談の上、お求めください。
ブログ日記BLOG
カゼのタイプをご存知ですか?
2013/01/21
冬から始める花粉症予防
寒さの厳しい日々が続きますが、花粉の季節はもすぐそこ。中医学には「春病冬治」といって、”冬の間に身体を整え、春の病気を防ぐ”という考え方があります。つらい症状を和らげるためにも、今からしっかり体質を整えて、花粉に負けない身体をつくりましょう。
 身体の防衛力アップで花粉をガード
身体の防衛力アップで花粉をガード
目には見えない気の存在
春は多くの人が花粉症に悩まされます。自然界では「風(ふう)」が活発となる季節で、過剰になると邪気「風邪(ふうじゃ)」となって花粉やウィルスなどを運び、体内に侵入させます。
中医学には二千年も前の医学書ですでに「正気存内、邪不可干」という言葉があります。「正気(せいき)」が身体の中に充実していれば、外部の邪気(病気の原因となるもの)の影響は受けないという意味です。正気はすなわち、生命機能の総称であり、身体の抵抗力を表す「気」と言えるでしょう。
また、身体の表面(鼻やのど、皮膚などの粘膜)をバリアのように覆って保護する「気」を「衛益(えき)」といいます。衛益は体表を巡り身体を温め病気の侵入を防いだり、毛穴の開閉をコントロールして発汗を調節する役割を担っています。毛穴は気門とも呼ばれ、邪気に侵入口ともなります。衛益が充実していれば花粉やウィルスなどの侵入を防御できるというわけです。
気の存在は目に見えませんが、病が侵入しないように身体を守り、病気の初期には体内の邪気と戦って撃退したり、病後の体力を回復させたりと、身体を守って元気に保つ大切な役割を担っています。
花粉症は命に関わる病気ではありませんが、頻繁に出るしゃっくりや鼻水、鼻づまり、それに伴う思考力低下など、日常生活の質を大きく低下させる不快なものです。中医学の春病冬治の考えに則り、症状が出る前から体質を整えて、春を迎えたいものですね。
花粉に備えるカラダづくり
「冬からの予防」
予防のカギは「気」。まず「肺」と「脾胃」を元気に。
「良い医者は未病を治す」。中医学にはこんな言葉があるほど、病気を未然に防ぐことを重視しています。花粉症も、症状を抑えるだけでなく、まず症状がなるべく出ないよう予防することが大切。冬の間に体内に「気(エネルギー)」を充実させ、花粉に負けない身体づくりをめざしましょう。ポイントは、「肺」と「脾胃(ひい・胃腸系)」を元気に保つこと。気は、おもに肺が取り込む酸素や、脾胃が消化吸収する栄養素から生み出されます。また、肺は「衛益(身体の防衛力となる気)」を全身に巡らせる働き、脾胃は体内の水分をスムーズに巡らせる働きをそれぞれ担っています。そのため、肺や脾胃が弱くなると、体の防衛力が低下したり、水分が停滞して鼻炎を招いたりと、花粉症の重い症状を引き起こす原因にもなってしまうのです。日ごろから風邪をひきやすい人、呼吸器系が弱い人、胃もたれや食欲不振といった胃腸の不調を感じている人などは、特に意識して肺と脾胃を整えるよう心がけてください。
 肺の元気が足りない人は
肺の元気が足りない人は
こんな症状に注意!
息切れ、風邪をひきやすい、汗がでやすい、顔色が白い、呼吸器系が弱い、舌の肥大
食の養生
○肺に潤いを与え、働きを良くする食材
白きくらげ、ユリ根、はちみつ、豚足、鶏手羽、など。
☆よく使われるのは
衛益顆粒(えいえきかりゅう)、八仙丸(はっせんがん)、双料参茸丸(そうりょうさんじょうがん)など
 脾胃の元気が足りない人は
脾胃の元気が足りない人は
こんな症状に注意!
倦怠感、胃もたれ、お腹が張る、食欲不振、軟便、顔色が黄色い、手足が冷える、舌のコケが多い。
食の養生
○脾胃を養い、元気をつける食材
米、大豆製品(豆腐、湯葉、豆乳など)、イシモチ、インゲン豆、棗、リンゴなど
☆よく使われるのは
健脾散(けんぴさん)、健胃顆粒(けんいかりゅう)、補中丸(ほちゅうがん)など
花粉症に効くツボ
手:合谷、魚際
顔:上迎香、迎香
首:風池
 症状が出てしまったら「花粉症の対処法」
症状が出てしまったら「花粉症の対処法」
同じ花粉症でも、体質や気候などの違いよってその症状は異なります。自分に合った対処法を知り、原因から症状を改善することが大切です。
花粉症の共通症状
目のかゆみ・赤み・腫れ、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、鼻のかゆみなど。この他、タイプによって特徴的な症状があります。
身体が冷える寒タイプ
寒さがまだ残る春先に多いタイプ。身体が冷えやすく、水のような薄い鼻水やくしゃみが多く出ることが特徴です。身体をしっかり温めて、体内から冷えを追い払いましょう。
症状の特徴
寒気、薄く透明な鼻水、くしゃみ、頭痛、舌の苔が白いなど
食の養生
○身体を温め、冷えを追い払う食材
生姜、ネギ、三つ葉、香菜、しなもん、こぶし茶など。
☆よく使われるのは
頂調顆粒(ちょうちょうかりゅう)、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)
のどの痛みがある熱タイプ
暖かくなる春先に多いタイプ。身体の熱感や喉の痛み、粘りのある鼻水などが特徴です。まず身体にこもった熱を冷まし、喉や目の炎症を抑えて症状を和らげましょう。
症状の特徴
発熱、熱感、目の充血、かゆみ、喉の痛み、口の渇き、粘りのある鼻水、舌が紅い、舌の苔が薄黄
食の養生
○身体の熱を冷まし、すっきりさせる食材
菊花茶、すいかずら茶(金銀花茶)、ミントティー、牛蒡、タケノコ、など
☆良く使われるのは
天津感冒片(てんしんかんぼうへん)、鼻淵丸(びえんがん)、麻杏止咳顆粒(まきょうしがいかりゅう)、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)、板藍根(ばんらんこん)など
鼻水や痰が多い湿タイプ
春の後半の花粉症に多いタイプ。体内に余分な水分が溜まっているため、鼻水の量が多い、痰が出るといった症状が現れます。滞った水分を取り除き、身体をすっきりさせましょう。
症状の特徴
頭重、鼻水の量が多い、痰がでる、むくみ、舌のコケがネバネバする
食の養生
○余分な水分をきれいに出す食材
しそ、ハトムギ、ドクダミ茶、冬瓜、杏仁(杏仁豆腐)など
☆良く使われるのは
勝湿顆粒(しょうしつかりゅう)、瀉火利湿顆粒(しゃかりしつかりゅう)、五苓散(ごれいさん)、二陳湯(にちんとう)など
 暮らしのワンポイント
暮らしのワンポイント
●早起きして腹式呼吸を。朝の陽気を身体いっぱいに吸い込みましょう。●辛い、油っこい、甘いもの、乳製品は控えめに。新鮮な野菜はたっぷりと。●夜のコーヒーやお茶はなるべく控え、質の良い睡眠を。●外出時はマスクやメガネを忘れずに。帰宅後のお風呂はシャンプーから。●洗濯物は室内干しが基本。外出後の衣類は外で花粉を払い落として。●便秘の改善も、つらい症状を和らげるポイントに。
チャイナビュー No.170『漢方の知恵袋 花粉症の養生』 中医学講師 菅沼 栄監修より
2013/01/18
陳先生インタビュー
Q. 日本語がお上手ですが、勉強されたのですか?
A. 中医大学の時、 中医学の研究や東洋医学が日本で盛んに研究されていることを知り、これから中医学の分野で日本との交流が多くなると思ったので、 大学の授業で日本語を選択し、 2年間勉強しました。「あいうえお」から勉強しましたが卒業時にはほとんど忘れていましたけど…(笑)
Q. 日本に来てからどのくらいですか?きっかけは?
A. 今年の9月で16年目です。93年「日中医学協会」 の招きで研修のため来日しました。 1年間研修後、「日本で学位を取りたい」と思い、広島大学へ。生命薬学科というところで、 薬の実験などをやっていました。 そこで薬学博士を取りました。
Q. 日本の生活はどうですか?
A. 便利ですね。食べ物は、最初から問題はなかったけど、 納豆がちょっと苦手です。 刺身は大好き!お寿司も大丈夫です。もずく・なまこも美味しいですね。
Q. ご出身は?
A. 江蘇省 揚子江の海への注ぎ口 南通(なんとん) の海門という所なので、 気候は温かく、日本に似ています。梅雨もありますし、四季があります。
Q. 中国にいらっしゃったときのご専門は?
A. 中医温病学です。
Q. なぜ 「温病学」を専攻されたのですか?
A. 半分は訳が分からずでしたが、臨床が好きなので、 基礎と臨床の間に位置する学科である「温病学」を専攻しました。大学に入った時の「温病学」の研究室が、全国で一番有名で「重点化学」 と言われ国から投資を受けて発展させるという時期だったので、それに憧れて温病の研究をしようと思いました。
Q. 日本では?
A. 中国では温病中心でしたが、日本の臨床では外感病、 特に呼吸器系の疾患がメインでした。東京医科大学の呼吸器系内科で研修もしました。
Q. 日本の漢方についてはどうおもわれますか?
A. ある大学病院の漢方外来では、 あるお薬が効くと知ったらそれを特効薬として多用されますが、それはとても疑問に感じました。
日本に「中医学」はまだまだ浸透していないと思いました。漢方薬を使うにはやはり「弁証論治」 が必要です。 個人の体質により効くお薬は異なってきます。漢方薬の使い方を病院の医師や患者さんに伝えました。
Q. なぜ、中医学を志したのですか?
A. 私は子供の時からあまり体が丈夫ではなかったし、 母も病気がちでした。たまたま、親戚が、軍隊の病院で働いておりました。診察している所を見ていた時、 煎じ薬で非常に効果があったのが印象的でした。
小さな都市では、中薬を煎じて飲む場合は 病気が重い場合か、難病しか無かった。それに接し、「医者になりたい」と思い、 医学部を受験しようと思いましたが、それまでは、中医学でも、西洋医学でもどちらでも良かった。入学当初は、中医学の勉強が難しくて、 「こういう勉強は面白くないな」などと思っていました。当時学校で、専門教育に根ざした人を作ろうと中医学の先生に説得されて中医の道へ。
本当に興味が出たのは、臨床に入ってからです。実際に臨床見学などをして、『患者さんが薬を飲んで元気になった』そういう光景を見て、 やりがい・ 勉強の価値があると感じました。
Q. それからやっとやる気になったんですね(^-^)。
A. そこまでは「やらされている」 といった方があっているでしょうか。中医学は難しい! 「黄帝内経」とか「傷寒論」など 古い漢文を読まなければいけないのは大変ですね。
Q. 中国の人が 中国語を読むのも大変なんですね。(^^;) 日本人のお客様に漢方の説明をするのは大変ですか? 違いなどはありますか?
A. まず違うのは、日本と中国のサービス業界全体の違い。 これは大きな社会的背景ですね。 (^^;あと、日本の方は病気に対して、西洋医学や養生の知識が高い。 そこでいきなり中医学の話をしても訳が分からないので、西洋医学と中医学をミックスしてわかりやすく説明することを心がけています。
具合の悪い原因が、 “気”の巡りが悪い事によって起きている病気でも、日本の方には「気」の概念がないので、「気のせい?」 と思われるようです。文化の違いですね。(^-^)
Q. 実際に臨床で診ている患者さんはどういった方が多いですか?
A. さまざまですが、高齢者の養生のため 難病、 西洋医学ではさじを投げられたような方々…リウマチなどの免疫性疾患や、喘息など。おそらく日本の社会的な構造からだと思いますが、 ストレスから起きる憂うつや不眠、自律神経失調。あと、不妊症の方なども多いです。
日本では不満があってもけんかしないから、よけいストレスが溜まってしまう。中国でしたら不満があったらその場でけんかしてしまうので、 解決してしまうんです。肝鬱はいろんな病気を引き起こす原因だったり、かねている場合が多いです。喘息や、 不妊症などいろんな疾患はストレスも絡んでいますね。
Q. 日本人はストレスを感じやすい、繊細というか、細かいというか・・ですね。
A. どの病気を考えても、 ストレスは切っても切れないものですね。中医学的にいえば 「気滞血オ」を引き起こします。 日本の社会と生活習慣で血液の流れが悪くなっている人は実際多いですね。
Q. 先生の好きな分野は?
A. 不妊症です。日本は人口出生率が低いし、 近い将来大きな社会問題にもなるかもしれません。 それと、不妊症の補助治療(体外受精など)も進んでいますが、成功率は三割程度です。 中医学をミックスすることによって、中医中薬の威力・持ち味を出せると思います。
中国でも現在は西洋医学・中医学を結合させた治療をやっています。不妊症は女性だけではなく男性にも原因があります。中国では婦人科・ 男性科がともにあるんですよ。双方の体調を整える事が大事です。
Q. ありがとうございました。ほんとに流暢な日本語でお話される陳先生。 不妊症の講議などで地方に行く事も多いそうです。御活躍を期待しております。最後に、お休みはどんな過ごし方をしていますか?
A. もっぱら子供と遊んでいますね。(^-^) あとは、 テレビを見たり・・・ 主にニュースやドキュメンタリーみたいなものをよく見ます。 動物番組も好きでよく子供と見てます。
2013/01/01
包先生インタビュー
中医学の普及のために全国で公演や勉強会を開催し、薬剤師などに中医学の教育をし、大活躍の包先生にインタビューをさせていただきました。
Q. ご出身は中国のどちらですか?
A. 内モンゴル自治区です。中国の北部、国境を挟んですぐ北はロシアです。草原地帯ではパオ(移動式の住居)での生活でした。
私がモンゴルにいた頃、買い物や映画を見に行くには馬で!だから乗馬はとっても得意ですよ!!モンゴルの人の顔立ちは、寅さん(映画“ 男はつらいよ”の)に似ていると、日本に来てから思いました。
Q. 包先生が日本にいらっしゃったのはいつですか?
A. 91年に東京医科大学への留学が最初でした。
Q. 先生のご専門は?
A. 中国では精神科、不妊、婦人科の症状を主に診ていました。
日本の薬局でも不妊や婦人科トラブルで悩む女性のメンタル面のケアもしています。
Q. 日本語は当時から上手だったのですか?
A. 中国にいたころから日本に興味があり、10年かけて学びました。初め、独学で勉強をしていたため、とっても大変だったことを覚えています。
Q. 日本へいらした理由は、やはり勉強ですか?
A. そうです。留学生として来ていたのですが、大学で博士号を取得したいと思い、それから中国へ帰ろうと考えていました。また、日本がどういう国か知りたかったからです。(日本好きのお母様の影響もあるようです)
Q. でも、そのまま日本に?
A. そうなんですよ。日本にはもともと興味があったと言いましたが、住んでみると思い描いていたよりももっと良かった訳です(笑)。そして自分の子供にも、是非この日本で教育を受けさせたいと思うようになったのです。
Q. 日本の好きなところは?好きな芸能人とかいますか?
A. 好きなところはいっぱいあります。綺麗で、何でもやりやすい、夢があれば実現できる、頑張れば成る国、ルールがしっかり決まっている、サービスは世界一・・・逆に、目標ないことが私は好きではありません。
日本で出来ないのは自分のせいと思って何事も頑張ることが大切だと思っています。
好きな芸能人は久本雅美さん。面白いだけではなく、誰にでも優しく、気遣いが細やかで何しろ礼儀正しいところが好きです!(一度お会いしたことがあるそうです)
Q. 体調のことで悩んでいる皆様にアドバイスをお願いします。
A. 日本でも中国でも、ご自分の体調について詳しく話を来てくれる所がまだまだ少ないのが現状だと思います。
女性も男性も、メンタル面の相談はとても大切です。不妊症や婦人科疾患で悩む女性の中には、誰にも打ち明けられずひとりで辛い思いをしている方も多いと思います。薬局にいらっしゃるお客様のお悩みをお伺いして終わるのではなく、気持ちを理解してお客様との信頼関係をしっかりと築くことが大切だと思っています。
特に若い方には、誇りを持って頑張って欲しいですね。また、何かお体のことでお悩みを抱えている方、漢方薬でフォローできることは沢山あるので、ぜひ薬局の場を利用して悩みを打ち明けてください。いっぱい お話を聞いて、全力でフォローいたしますので。
最後に、不妊症でお悩みの方、妊娠できても、それが叶わなくても、一人の人間として不妊治療を頑張った自分を、常に褒めてあげてください。
これが私から皆様へのアドバイスです。
包先生は以前、作家の久美沙織さんとお話しする機会があったそうです。久美さんは、4 5 歳で自然妊娠、ご出産を経験された女性です。
ご自身の体験を経て「4 5 歳、もう生んでもいいかしら?」「ナチュラルな妊娠」を出版されました。まさに諦めない妊娠の代表ですね。
お忙しいスケジュールの合間でも、丁寧にひとつひとつの質問に答えてくださった包先生。優しく、お母さんのような雰囲気と同時に、熱心で、常に努力を惜しまない先生のお人柄、本当に素敵です。包先生に、あなたのお悩みを打ち明けてみませんか!!
2013/01/01
仝先生 インタビュー
Q. 先生のご専門は耳鼻科と内科とお伺いしております。日本人は花粉症をはじめ、 アレルギー疾患でお悩みの方がとても多いと思うのですが、日本に来られて、その辺りの事はどの様にお考えでしょうか。
A. やはり日本人には花粉症などアレルギー疾患の方が多いように思います。私が来日して非常に強く感じたことは主に二つあります。
ひとつは日本人の食生活が西洋化していること、冷たいものをより好んでとることです。日本人は外食などで洋食を食べ、 季節に関係なく冷たいものを当たり前のように口にしていますね。冷たいものはもちろん体温を下げますので免疫力も低下します。
アレルギー疾患の発症は免疫力の低下とおおいに関係していますのでアレルギーを起こしやすい体質を作ってしまいます。中国では、 真夏でも空港などでは温かい緑茶が売られていて冷蔵庫から出したばかりの冷たい飲み物はあまり売られていません。 みんな温かい飲み物を飲んでいます。
ふたつめは、特に若い人が薄着であることですね。通勤時、駅のホームでミニスカートの女子校生が非常に多いことや、 両親は厚着なのに一緒にいる小さな子供だけ半ズボンで薄着といった光景には驚きました。
Q. なるほど~。そうすると中国の方は体を冷やす物や洋食はあまり食べていないのですね?
A. もちろん、中国でも洋食を食べている人もいますよ。けれど、 中国人は野菜たっぷりのお鍋やしゃぶしゃぶ、中華料理など温かい料理を好みますね。焼肉はあまり好んで食べないかもね。やはり伝統的な食事、 日本だったら和食が健康的な体質を守るのだと思います。
Q. 実際に臨床では、どの様なご相談をよく受けられますか? また何かアドバイスがございましたら是非お願いします。
A. 女性のお客様からは生理不順など婦人科系疾患や冷え、鬱症状など、 男性のお客様からは生活習慣病やがんなどのご相談をよく受けます。もちろん、 私の特に専門としている耳鼻科系の疾患に関してもお受けしております。
どの疾患でも、ポイントは①和食を食べる ②コーヒーは飲み過ぎない。緑茶や養生茶がオススメ。だと思います。
Q. 今、“養生”という言葉が出てきましたが…。先生はよく“養生” に関してもアドバイスをされていますよね。日本のような四季のはっきりした国で、季節の変わり目に体調を崩す方も多いようです。 胃腸の弱い方も多いですし、最近、メタボなど生活習慣病も増加しています。何かオススメの養生法はありますか?
A. 中国には“春夏養陽 秋冬養陰”という言葉があります。文字通り、 “春と夏には陽を養い、秋冬には陰を養いなさい”ということです。つまり、春夏は体を冷やしてはいけないのです。
また、日頃の生活面では、寝る30分前は脂っこいものや甘いものは避け、どうしても空腹なら、 消化しやすい食パンなどの炭水化物をとるように。アルコールも適量(個人差はあります)ならば健康の助けになるでしょう。
Q. 先生のご略歴の中に、“耳鼻喉学術経験継承人”とありますが、これは何ですか?
A. 臨床経験を何十年も積んだベテランの中医師である老中医のもとで、 3年間指導を受け弟子入りすることです。高齢化や海外進出などで老中医が減少し、伝統医学を後世に伝えることが出来なくなることを懸念し、 中国政府が始めた制度です。この老中医の生徒に選ばれる選抜条件は厳しいですよ。
Q. その厳しい条件をクリアし名老中医のもとで学ばれて、 その後は臨床で沢山の患者さんの診察をされていたのですね。スゴイ!!ところで、先生は日本に来られてわずか5年程ですが、 日本語もお上手ですよね。日本語学校に通われたのですか?
A. 学校へ行く時間はなかったので、 日常の人との会話の中で日本語を学びました。ただ、来日したての頃は、日本語の音を上手く使い分けられず、タクシーで “あのビルの前でおろして”と言いたいのに“あのビルの前でころして”と言って運転手さんをびっくりさせてしまったり、 肩こりでご来店されたお客様との相談で、“きんにくの凝りが~”と言ったつもりが“にんにくの凝りが~”になってしまったり(笑)
今も、常に持ち歩いている大切な日本語の日常会話の本を見せていただきました!
Q. 母国中国で、先生のオススメの場所はどこですか?
A. 故郷の河南省鄭(てい)州ですね!河南省は、中国では「医聖」 と呼ばれる張仲景の故郷です。また少林寺拳法や陳式太極拳の発祥地でもあります。小さな子供から大人までみんなやっています。 世界的に有名な“洛陽水席(らくようすいせき)”というたっぷりの野菜や肉を使ったスープ料理が美味しいですよ。
Q. いつか訪れてみたいですね。では日本での生活はいかがですか? 日本食はお好きですか?
A. 日本は、どこに行っても中華料理屋もあるし食事には慣れました。 日本食で一番好きなのは“カレーうどん天ぷらのせ”です。お刺身や納豆はまだ慣れていません。家では、 よく自分で皮から具まで全て手作りで餃子を作ります。冷凍保存で2週間は食べられますよ!
Q. 皮から作る餃子、本格的ですね!!では先生のご趣味はお料理ですか!?
A. いえいえ・・。趣味は、リラックスした状態で、 自宅でテレビや映画を観たり、音楽を聞いたりすることです。たまに書道もします。
Q. 最後に、これから漢方で体質改善したいと考えている皆様にひとことお願いします。
A. 漢方治療は焦らず落ち着いて。 少なくとも3か月~半年服用するのは基本です。またご自分の生活習慣をよく見直した上で漢方薬をお飲みください。
仝先生、インタビューにお答えいただきましてありがとうございました。
2013/01/01



