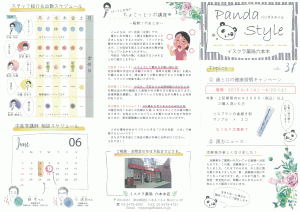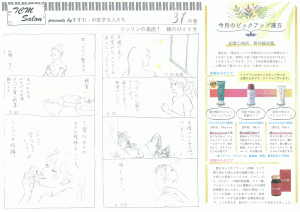ブログ日記BLOG
月経困難症、生理痛の気滞瘀血について ~タミーの月経講座~
2019/07/13
子宮筋腫、子宮内膜症の中医学 ~タミーの月経講座~
【癥と瘕】
中医学的な癥瘕の分類
下記のどのタイプでも気血の失調が大元にあるといえます。
2019/07/13
もーりー先生の髪のトラブル漢方養生講座
こんにちは!もーりーこと鮎澤です!
今回は髪のトラブルと漢方的養生についてお話します。
まず美髪の条件はハリ・コシ・ツヤです。全身栄養状態と老化のレベルを反映します。
抜け毛は、主に加齢、ホルモンバランスの乱れが原因。しかし最近では20代前後の若い女性が抜け毛に悩むことが多いそうです。過労や食生活の乱れが原因かもしれません。
また女性の薄毛は、びまん性脱毛症(髪の毛が全体に薄くなり、一本一本が細くなる症状)によって起ることが多く、進行するとつむじハゲも気になります。頭皮の見え具合と分け目の目立ち具合はつむじハゲを発見するきっかけとなります。
びまん性脱毛症の原因として
◎加齢
〇過度の食事制限によるダイエット(栄養失調を起こし、毛髮の発育を妨げる)
〇ストレス
〇過度のヘアケア―
〇避妊用ピルの連用・・・
などがあります。
中医学では、「腎の華は髪の毛にある」という説があります。「腎」の機能とは、内臓の一つを指すのではなく、泌尿生殖系、ホルモン系、自律神経系、カルシウム代謝、免疫などを含んでいます。
「髪の毛は血(けつ)の余り、腎の華」
「血」とは、血液をさし、全身のあらゆる組織や細胞に栄養や潤いを運びます。
栄養失調、貧血状態では、髪の毛の潤いが足りなく、パサパサ、薄毛、白髪も出やすくなります。
健康な髪を育てるには、毛母細胞を活性化させ、丈夫な毛根を作る鉄分や亜鉛などのミネラルが必要です。
鉄分には、血液中のヘモグロビンを作り、血流を介して髪の形成をサポートする働きがあります。
亜鉛は、髪の材料となるケラチンの生成、成長に欠かせない成分です。
ミネラルは体内で作ることはできず、食べ物など体外から摂取するしかありません。
そして女性は月経、妊娠、授乳とミネラル(鉄分)を消耗しやすいです。
しかし、鉄分は銅や亜鉛、ビタミンB12、葉酸などの栄養素がひとつでも不足すると、鉄分を摂取しても貧血の原因となってしまいます。また、亜鉛不足も貧血の一因といわれ、ヘモグロビンそのものの生成が上手くいかなくなります。
ミネラルには、似通った性質のミネラル同士はおたがいの吸収や働きを妨げる場合があります。鉄分だけを多量に摂取した場合、亜鉛や銅の吸収が妨げられ、亜鉛を多量に摂取した場合、鉄分や銅の吸収が阻害され、貧血になることもあります。
あくまで食事で足りない分を補う補助食品とし、食べ物からバランスよく摂取することを心がけたいですね。
「血」も食事の消化・吸収から生み出されます。髪の毛の栄養分は「血」によって補給されます。
「腎」における「腎精(じんせい)」の充実は、中医学で髪の毛を美しさする第一ポイントです。
それ以外に、「肝(かん)」や「肺(はい)」も髪の毛の質や潤いに影響を与えています。

【中医学「血」から見た薄毛、脱毛について】
気血両虚・・気(体のエネルギー)と血の不足
【症状】
・毛髪が乾燥して艶が無く切れやすい。色が白っぽい又は薄茶色っぽい。
・頭全体が脱毛し易い
・顔色に艶がない。唇が白い
・動悸、息切れ
・食欲不振
・疲れやすい
・めまい
・月経不順
・月経の量が少なく、経血が薄い
・産後、授乳中・・・
【食養生】 ・大豆製品、小麦、豚肉、羊肉、鶏肉、卵、レバー、カボチャ、山芋、ニンジン、ほうれん草、クルミ、黒胡麻、栗、ナツメ、クコの実、黒砂糖・・
【鉄分を多く含む食材】 ・ほうれん草、大豆食品、アサリ、シジミ、ナッツ類、ヒジキ、ワカメ、海苔、ココア・・
【亜鉛を多く含む食材】 ・牡蠣、ホタテ、ウナギ、シジミ、牛の赤身肉、豚レバー、納豆、高野豆腐、チーズ類、松の実、カボチャの種、卵・・・
以上です。
もーりー先生の過去の記事はこちら↓
2019/07/12
季節から見る皮膚シリーズ③ 梅雨の時期は体の水はけをよくして、肌代謝を上げよう
こんにちは。車田です。
おそらくあまり大好きな人はいないであろう、梅雨のシーズンがやってまいりましたね。この時期に気をつけていただきたいのは、体内の水はけ。ただ息をしているだけで、水分を取り込んでしまっているので、体内も水浸し状態になりがちです。

中医学では、体にとって必要のない水を「痰」とか「湿」などといいます。これらが慢性的に体に溜まり始めると、重だるい、食欲が出ない、むくみなどといった症状が出てきます。この湿が原因で皮膚疾患が悪化する方は、体内の水はけをよくすることがポイントです。
シリーズ第三回目の今回は、湿と皮膚疾患についてです。

この時期に起こりやすい皮膚疾患として、湿疹があげられます。中医学において湿疹は、体内に溜まっている湿を皮膚から出そうとして出しきれなかったものとされます。とくに、汗腺の多い手のひらや足の裏などに水疱ができる場合は要注意。早めに対処していかないと、毎年梅雨の時期になると繰り返す…ということになりかねません。すでに慢性的な皮膚疾患をお持ちの方も、このシーズンは特に湿に気をつけてコントロールする必要があります。
また、この時期の日本列島は4つの気団のせめぎ合いにより、湿にプラスして暑さと寒さも入り混じります。気圧の変動プラス寒暖差ということです。この事により、自律神経のトラブルも起こりやすいので注意が必要です。
そして当たり前のことですが、人の体は食べたものからしか作られません。体に湿が溜まる最大の要因は食事です。自分で今からできる養生でもありますし、一番身近な毒となる要因でもあります。食材もさることながら、食べ方も重要です。下記、まとめましたので、ご参考ください。
【湿を溜めやすい食材】
乳製品(チーズ、生クリーム、ヨーグルトなど)・小麦加工食品(特に菓子パンやケーキ、パスタなどの麺類やたこ焼きのような粉物系など)・砂糖・脂っこいもの・アルコール・冷たい食べもの(常温のものや、生のものも含みます)

【湿を取り除くおすすめ食材】
・ハトムギ茶
→湿を取り除くだけでなく、肌代謝も上げてくれるので、皮膚トラブルには重宝します。
温めも冷やしもしないので、どんな湿のパターンにも対応できます。
・赤小豆
→特に妊娠中のむくみによいとされています。砂糖と煮込むと利湿の働きが弱くなるので、そのままスープなどに入れて煮込んで召し上がるのがおすすめです。
・蓮の葉
→蓮の花は泥水の中でとても美しい花を咲かせます。清濁から清を分別することから、腎泌尿器系疾患にも応用されてきました。熱を冷ます働きがあるので、梅雨の後半、夏に向けて気温が上がってくる時期や、湿+熱の症状がある方に◎

【食べ方】
基本的に、体温より高い状態で摂取することをおすすめします。
体内に熱がこもっている場合でも、寒性や涼性の食材を選び、体温より高い状態で摂取することで、食材の持つ作用をしっかり吸収できますよ。すべての食物に火を通さなくても、トータルの温度が温寄りであればOK。たとえば、お刺身を食べるときは必ず、温かいお味噌汁やお茶とセットにするなどです。
皮膚に疾患がない方でも、季節の養生になりますので、ぜひご参考ください。
梅雨の季節もどうぞ健やかにお過ごしくださいね。

2019/06/12
六本木 Panda Style -パンダスタイル- #37
2019/06/11