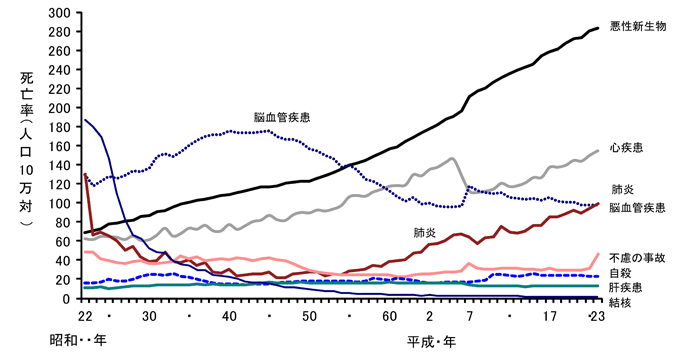こんにちは。店長の櫻井です。今日、1月25日は、【主婦休みの日】だそうです。なんとそんな素敵な日があったのですね!
【主婦休みの日】は、『年中無休で家事や育児にがんばる主婦が、ほっと一息ついて自分磨きやリフレッシュするための休日が「主婦休みの日」で、1月25日、5月25日、9月25日が記念日。女性のための生活情報紙を発行する株式会社サンケイリビング新聞社が中心となり制定。日付は年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みなどの主婦が忙しい時期のあとの年3日を設定したもので、日頃は家事や育児を主婦に任せがちなパパや子供たちが家事に取り組み、その価値を再認識する日との提唱も行っている。』(みーちゃんの今日は何の日より)だそうです。
ご主人が毎日清潔な服をきて会社にいけるのも、学生さんが毎日おいしいご飯を食べられるのも、休みなく働くお母さんがいてくれるからです。今日はしっかりと家族サービスならぬ、「主婦サービス」しましょう!
今日はまた、日本最低気温の日でもあるそうですので、寒い日は肌が乾燥したり、血流悪くなって頭痛くなったり、肌が乾燥したり、カゼひいたり、肌が乾燥してがびがびになったりするので、お肌の潤いにもよくて、血流にもよくて、免疫力も強化してくれる『納豆』のお話をしたいと思います。お肌に納豆が良いっていわれてなんだかぴんとこないとは思いますが、これがいいんです。
別名、畑のお肉と言われるほど、良質なたんぱく質と脂肪分を含んでいる大豆ですが、生のまま食べると毒があって食べられないのはみなさんご存知でしょうか。なので、炒ったり煮たりして火を通して無毒化して食べるんですよ。でも炒った大豆はそのままでは硬くて消化されにくいという欠点も。そこで、そういった欠点を解決してくれるのが『納豆』です。納豆は納豆菌により、消化されやすくなり、タンパク質や炭水化物、脂肪分などの栄養素をそのまま残してくれた、栄養食品なんです!
納豆の歴史
納豆は縄文のころににはもう日本に入ってきていた大豆と、たまたま住居の建材としてそこにあった藁で、これまたたまたま、偶発的に作られたのが始めと考えられていますが、いまだその起源はくわしくわかっていません。ちなみに納豆は日本独自の食材で、ほかの国にはない、純日本食材なんですよ。
『納豆』という名前が初めて書物に残されたのは、平安時代、11世紀半ばごろに藤原明衡によって書かれた『新猿楽記』です。その中で、納所という「お寺の倉庫で作られた食品」として紹介されています。
戦国時代には、武士たちの貴重な蛋白源やスタミナ源としての保存食・軍事食として、そして江戸時代には、庶民の栄養食として食べられていたようです。当時は納豆ごはんよりも、納豆を味噌汁にいれた納豆汁の方が一般的だったそうです。
納豆の栄養
「納豆どきの医者知らず」という諺があるのを皆様ご存知でしょうか。
栄養豊富な納豆をしっかりたべると、体力も気力も充実し、病気に負けない身体ができて、医者にかかる人も少なくなってしまうという意味です。納豆には、良質で豊富なたんぱく質に加え、ビタミン類やミネラルなどもたっぷり含まれています。中でも特筆すべきは「ナットウキナーゼ」、「レシチン」、「ビタミンK」そして「ポリアミン」。これらを順に見ていきましょう。

2010 Japan Trip 1 Day 2 / tofuprod
『ナットウキナーゼ』とは、強力な血栓融解酵素のこと。ナットウキナーゼが人体の血栓を溶かすという研究報告はまだないのですが、動物実験では、その効果が確認されていますので、これからの研究に期待です。しかし、研究結果がないからといって、そっぽを向いてしまうのはもったいないですよね。血栓が解かされるということは、血液がさらさらと流れやすくなるということ。血流は心臓の拍動だけでなく、筋肉によっても流れているので、筋肉の活動が少なくなる夜のほうが悪くなります。納豆を血流改善に生かしたいのなら、納豆は夜たべるのが効果的と言えるでしょう。でも食物繊維が多いので、胃腸の弱い方、便秘気味の方、お腹が張りやすい方は、消化能力が高い朝に食べるほうが良いですよ。
血流が悪くなると、お肌に老廃物が溜まりやすくなったり、潤いが届きにくくなったり、シミやくすみが出来たりします。冬場に肌が乾燥するのは、単に空気が乾燥しているからだけではありません。寒さにより無意識のうちに体に力が入ってしまうことで、血流も悪くなっているというのもその原因の一つです。お肌を潤すためにもしっかり血流改善対策をしていきましょう。
次にビタミンKですが、納豆に含まれるビタミンKは食品の中でもトップクラスです。ビタミンKは骨を作るうえでとっても重要なビタミンで、カルシウムを骨に結合させるのに必要なビタミンなので、納豆は、骨粗しょう症の予防にも効果的です。他の食品、例えば、紫蘇、パセリ、モロヘイヤなんかにもビタミンKは多いのですがそれらを毎日沢山食べるのはちょっと難しいですよね。
そして「レシチン」です。レシチンには腸のなかをきれいにしてくれる排毒洗浄作用があるとされています。これまた納豆にたっぷり含まれている食物繊維と協力し合い、胃腸を掃除してくれ、ニキビや肌荒れ予防・改善にも効果的です。さらに納豆菌の一部は生きて腸までとどき、ビフィズス菌のえさになることで、腸内環境を改善してくれます。腸内環境を改善することは、美肌だけでなく、大腸がんの予防や花粉症などのアレルギー症状の軽減など、たくさんのいいことがあります。

納豆ねばとろ。ネギも入れてほしいね(笑) / klipsch_soundman
「ポリアミン」という成分も含まれています。これは細胞分裂やタンパク質の合成に関与する物質で、赤ちゃんに多く、加齢とともに減ってしまう物質んなので、別名「若返り成分」。ポリアミンが無いと細胞は分裂・増殖できません。しっかりとって、張りと艶のある肌を保ちましょう。
中医学的に納豆をみると
温性で身体を温めてくれます。薬膳でも納豆は、血行不良である「瘀血」を改善し、冷え性を改善する代表的な食べ物です。冷えや肩こり、美肌、生活習慣病の予防から、更年期障害の症状の改善にもおすすめできる食品です。
納豆がお肌に効く理由は、栄養と保湿成分をたっぷり含んでいて、細胞を元気にして、腸をきれいにするためです。高価な化粧品より納豆の方が断然リーズナブルで、効果が高く、さらに美肌以上のメリットがありますし、おすすめです。お薬やサプリではない、自然食品なので、毎日食べてることが大切です。毎日一パックで十分なので、お試しくださいね。
そして、納豆の有効成分は熱に弱いので、出来るだけそのまま食べるようにしてください。加熱する場合は、70℃を超えないようにしましょう。納豆は、一般的な製法で作られるより、自然製法で作られた藁の納豆の方が、納豆菌のパワーも、栄養も強く、もっとおいしいそうです。自然製法で作られた藁納豆はちょっと高価なので、毎日食べるにはぜいたく品かもしれませんが、月に1,2度ぐらい、身体へのご褒美としていかがでしょうか?
***facebook やってます! 「イスクラ薬局」でご検索いただくか、こちらのリンクをクリックしてぜひ「イイネ」をおしてください!***