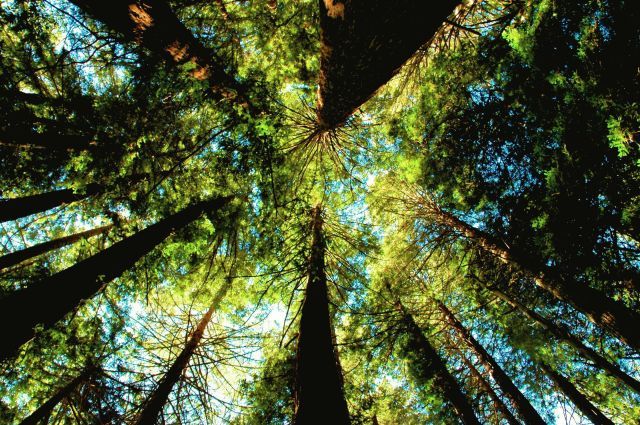こんにちは、櫻井です。今日はまたうちのパンダちゃんが吹き飛ばされてしまうぐらいの突風が吹いていますが、みなさんお怪我は有りませんか?こんなに寒くなってくると、冷えや痛みのご相談も増えてきます。冬場になると生理痛が酷くなるという方もいらっしゃいます。冷えは血の巡りを悪くします。流れが滞ると痛みの原因になるので、冷えは関節痛や頭痛、腰痛などを引き起こす原因になります。日ごろからしっかり防寒対策をして、温かいものをだけを食べるようにしましょう。
今日のブログでは、またまたツイッターにお寄せいただいたご質問にお答えしたいと思います。ツイッターでのご質問は「月経量の事で質問ですが、最近月経が2日間でほぼなくなってしまいます。元々、陰虚血虚です。ここは無難に当帰芍薬散でしょうか?年齢は40です。」という物でした。このご質問にお答えするには、まずは月経についていろいろお話しなくてはいけません。まずはそこから初めてみたいと思います。
「月経」とは生理のことです。生理は女性の健康のバロメーターです。女性は一生のうちに約35年間生理とのお付き合いがあるとされています。「正しい生理の状態」を知ることで、自信の健康を管理することが出来ます。子宮は経血をめぐらせる場所です。妊娠の準備をするため、子宮は古い血を捨てて新しい血に交換し ようとします。この古い血液を排出しようとする作用が「月経」です。

正常な生理の目安をまずは見ていきましょう。(パンフレット「生理痛はないのがあたりまえ!」より)
初経発来: 10~14歳
生理周期: 25~38日 生理周期とは、生理初日から次の整理の前日までの日数です。一般的に排卵を伴う生理周期のことを指しています。この期間より短かったり、長かったりする場合は注意が必要です。ちなみに初潮後数年間は安定せず不順になることもあります。
生理持続期間: 3~7日 生理持続期間は経血が出始めてから終わるまでです。一般的に初めは多く徐々に少なくなります。年齢によっても違いますが、一般的にこの期間内であれば正常と言えます。この範囲未満、もしくはこの範囲を超える出血がある場合は注意が必要です。
経血の量: 約50ml~100ml(総量) 一般的に2日目が多く徐々に少なくなります。日中、昼用ナプキンを使用していて、1時間ほどで経血があふれるような状態が続くようであれば注意が必要です。
経血の色: 赤~暗紅色 月経中ずっと黒っぽい場合や、鮮やかな赤の場合は注意が必要。
経血の質: さらさらとした液状 血の塊、レバー状の塊、薄く水っぽい場合は注意が必要です。
生理痛: 痛みはほとんど無い
もちろんこれらの目安には個人差があり、その時の体調によっても変化しますが、目安として正常な状態を知ることで、体調の管理がしやすくなります。婦人のご相談の場合は、生理の状況を詳しく聞くことが大切です。特に生理の量、色、質、生理周期の4つを詳しくお伺いします。初潮年齢、初潮から2~3年後の状況と現在との比較も大切です。もう一点、オリモノの状態も体の中の状態を知るうえで大きな目安になります。健康なオリモノは、排卵期ごろに粘り気のある透明なオリモノが3日以上あることです。
次に月経周期から体の不調を見てみましょう。
月経周期が短いタイプ(25日以下)
・経血量は少なく、塊も少ないが、腰が痛いしだるいのは、「陰虚」(いんきょ)といって潤い不足である可能性があります。喉の乾き、目の渇き、寝汗、ふらつき、めまい、ほてり、手足のほてり、午後からの微熱などがみられることもあります。潤いは血の元なので、体に必要な血の量が少なく、経血が足りない状態です。陰の根本は腰にある「腎」という臓器にあり、腰が痛いのは腎の力が落ちていることを表しています。
・経血量が多く、色が鮮やかな赤、または深紅ならば、「血熱」(けつねつ)といって、血が熱を盛った状態を疑います。赤ら顔や唇の乾燥、のどの渇き、便秘など同時にみられることがあります。舌は紅い状態です。苔は黄色くなっている場合もあります。血が熱を持ち、暴れて出血している状態です。
・経血量が多く、色が薄い、腹部の張りなどがみられる場合は、脾(胃腸系)のエネルギー低下を疑います。症状はその他、オリモノが多い、むくみやすい、顔色は白または黄色っぽい、身体の重だるさ、手足のだるさ、便が柔らかい、または下痢なども見られることがあります。舌は全体的にむくんで大きくなり、歯形が付いていることもあります。苔は白く厚くなっている場合もありますし、一部はがれていることもあります。脾は血を体内にとどめる力があるので、それが低下して、漏れ出ている状態です。
・経血の量が多かったり少なかったりして、色は紫赤、もしくは暗い色。レバー状の塊や小さい塊があり、出血期間が短い場合は、「肝鬱化火」(かんうつかか)といって、気の巡りが悪くなり、熱を盛った状態を疑います。イライラ、抑うつ、乳房やわき腹の張りや痛み、下腹部の張りなども見られることがあります。自律神経系のコントロールがうまくいっていない状態です。
月経周期が長い場合(35日以上)
・量は少なくて、色が暗黒で小さな塊もあり、腹部の鈍痛を感じ、温めると良くなるのは、「陽虚」(ようきょ)というエネルギーの不足状態かもしれません。陽気は温める力があるので、不足すると冷え・寒がり、顔色の暗さなども見られます。陽も腎に蓄えられているエネルギーです。腎は腰にあり、腰痛は腎の弱まりを表しています。
・経血の色が暗い紫色で、大き目の塊があり、痛みは下腹部にあるが、温めると楽で、押したりすると余計に痛む場合は冷えが身体の中に固まっているタイプ。顔色が青白く、暗い。生理中にアイスクリームや氷が入っている飲み物など冷たいものをとる、水泳やスキューバなど水に入る、冬場の防寒対策ができていないなど外的要因により冷やされた場合に多く見られます。
・量は少なく、色が薄い。顔色も蒼白もしくは艶がない、めまいやふらつきがある、動悸が不眠がある、乾燥肌・髪などでは「血虚」(けっきょ)といって、血の不足を疑います。血が足りないので、しっかり出血しません。子宮内膜も薄くなっているかもしれません。血は身体を滋潤しているので、乾燥を感じます。便秘がある人もいらっしゃいます。
・経血の量は多かったり少なったりで、色は褐色っぽい色。生理前に痛みがあり、その他憂鬱寒、イライラ、胸の張りや痛み、下腹部の張り、生理がきて血がでるとすっきりするなどの場合は気の巡りが悪くなった、「肝鬱気滞」(かんうつきたい)状態と考えます。月経周期が短い場合も起こりますが、長い場合はイライラが少なく抑鬱が強く表れることも多いです。
・色が淡く粘っこいのは、「痰湿」(たんしつ)といって身体の中にいらないものが溜まってしまっている状態かもしれません。肥満、食欲不振、偏食、過食、白いオリモノ・黄色のオリモノ、臭いのあるオリモノなども見られることもあります。
その他、短くなったり遅くなったり安定しない不順型や、無月経などこのほか様々あります。
ではもう一度ご質問を見てみましょう。「月経量の事で質問ですが、最近月経が2日間でほぼなくなってしまいます。元々、陰虚血虚です。ここは無難に当帰芍薬散でしょうか?年齢は40です。」というものでした。冒頭でも触れましたが、婦人のご相談の場合は、生理の状況、特に生理の量、色、質、生理周期の4つの情報と、初潮年齢、初潮から2~3年後の状況と現在との比較、オリモノの状態などの情報が欠かせません。上記の質問をこれらに当てはめると情報が大きく不足していますので、「この薬があっています!」というアドバイスは残念ながら難しいです。
「当帰芍薬散」(とうきしゃくやくさん)についてご説明させていただきます。これはもともと、「婦人の妊娠時の腹痛」にた対してつくられた処方ですが、補血活血(血を補い流す)、健脾利水(胃腸の調子を整え、余分な水分をさばく)、調経止痛(経脈の調子を整え、痛みを和らげる)の力があり、血虚、脾虚湿盛の状態に対するお薬で婦人のみが対象ではありません。症状では、皮膚につやがない、頭がボーっとする、頭痛・手足のしびれ、月経料が少ない、月経が遅れる、月経痛などの血虚の症状。食欲不振、つかれ、顔や手足のむくみ、頭が重い、腰や四肢の冷え、腹痛、泥状~水様便、白いオリモノなど脾虚湿盛をともなうもの(中医処方解説)とあります。これらの症状がある場合には適していると考えられます。
そして、陰虚血虚状態(陰という潤いと血が足りていない状態)ならば、当帰芍薬散だけでは少し足りません。血を補う力が当帰芍薬散にはありますが、陰を足す力がありませんし、やはり包剤の力不足感がいなめません。当帰芍薬散に加えて補腎の薬が必要ですね。40歳という年齢から考えても、腎の機能低下を考え無くてはいけません。その他、血の巡りや気の巡り、各臓腑の機能状態と、何を目的として漢方を飲むのかなども考慮に入れてお薬を選ぶ必要があります。
***漢方の服用をお考えの場合は、お会いして、お話をお伺いすることがとても重要です。ネットや本の情報に頼らず専門家がいる薬局・薬店・病院でご相談くださいね。***
月経は一つの生理現象として考えることが出来ますが、本当は、生殖のための過程であって、目的ではありません。経血 が充満して子宮に注がれることの本来の目的は、子宮 を栄養し、卵子を準備し、妊娠出来る状態にすることです。妊娠している最中には月経がなくなるのはそのためです。妊娠し ていなければ次に妊娠するために古い血を捨て、新しい血と入れかえる、月経が行われるのです。そしてこの一連の働きは、体内の臓腑や気血などのバランスが整って初めて正常に行われます。西洋医学的に見ても、月経は目に見えないような量のホルモンの微妙なバランスの上に奇跡的に成り立っているように見えます。ちょっとしたストレスや寒暖の影響であっという間に崩れてしまいます。月経の状態に注意を向けて、健康維持に役立ててくださいね。