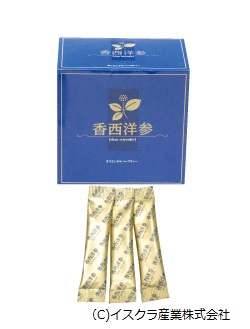昨今、女性が活躍する時代、とにかく女性は年中忙しいのです。
朝から夜まで仕事や勉強、仕事でもプライベートでも周りに気を配り、
結婚、妊娠、出産が加われば、自分のこと以外の家事、炊事、育児を両立…。

中医学でいう「血」は肝に貯蔵すると考えます。毎日元気に動けるのも、「血」が潤沢にあり全身を隈なく巡っているからなのです。
「血」の働きとは
・精神・意識・思考を安定させる
・肌や髪など身体を潤し栄養する
PCやスマホなど目を酷使する作業、脳を使う作業、運動、月経、授乳、夜ふかしなどで「血」は常に消耗していきます。
毎日の食事や睡眠で補えているかというと、足りていない人の方が多い印象を受けます。
あなたはどのタイプ?
①身体を潤し栄養する「血」が不足している「血虚」タイプ
□冷え症、手足やお腹が冷える
□疲れているのに眠りが浅い
□よく目が覚める
□夢が多い
□眠ったつもりでも朝スッキリ目覚めない
□物忘れ
□便秘気味
□気分が落ち込みやすい
□髪に艶がなく枝毛、切れ毛になりやすい
□爪が割れやすい
□疲れやすい
□立ちくらみ
□乾燥肌
□顔色が白い
食事や睡眠を見直し規則正しい生活から始めましょう。添加物や甘いものを止め、腸内環境を整えましょう。
卵、豚肉、鶏肉、牡蠣、黒豆、棗、など赤黒食材を積極的に食べてみましょう。
②過労やストレスで脳が疲れ「心血」と「脾気」が損傷している心脾両虚(しんぴりょうきょ)タイプ
□物忘れがよくある
□人の話を理解できない
□汗をかきやすい
□くよくよしたり不安感を感じやすい
□食欲が落ちている
□疲れやすい
□下痢or便秘
□経血が多い
□眠りが浅い
□眠れない
□めまいや立ちくらみがある
胃腸が弱り、消化吸収がうまくいかない方はまずはそこから立て直します。
食事をしてもそれをしっかり気(エネルギー)と、血(栄養)に変えられているかどうかも重要な点だからです。
食事から得られた「血」は「肝」に貯蔵され「心」のポンプで全身に隈なく巡ります。
冷たいもの、脂っこいもの、刺激のあるもの飲食を避け、よく噛んで腹八分目にしましょう。
生活のリズムを整え疲れを溜めないようにしましょう。
③ストレス、睡眠不足、目の使いすぎの陰血不足(いんけつぶそく)タイプ
□目がかすむ
□目が疲れやすい
□視力の低下
□目の充血、涙目
□ドライアイ
□口が渇く
□疲れやすい
□足が吊りやすい
□のぼせ、頭痛、めまい
□筋肉がつりやすい
□手足のほてり
□のぼせ、頭痛、めまい
□便秘
目をつぶる、これも血を貯蔵している「肝」の養生です。
早めに寝て睡眠時間の確保をしましょう。
すきま時間に目を閉じて、休ませてあげるのも立派な養生です。

いかがですか。
血虚のタイプも人それぞれ、原因を探りつつ、自分に合った対処をして、イキイキ艷やかな毎日を送ってみませんか。