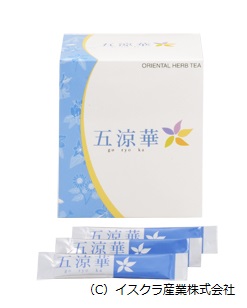こんにちは!中神です。
気象庁は「今年の夏の気温は平年より0.5~1.5度高く、昨年より0.5~1度高いと予想される」と明らかにしました(´・ω・)って…
私は昨年の夏、思いました…
「ゆで蛸になってしまいそう」
だと。
しかし昨年より今年の夏の方が暑いので、たぶん「揚げだこ」になると予想されます。素揚げの蛸、おいしいですよね。ビールと素揚げの蛸で一杯やりたい(´艸`*)
のですが、ビールと素揚げの蛸は夏最強の不養生だと思います!!!!なんの話だ…(笑)
そんなわけで、今回は夏の養生についてお話しようと思います。
夏は「心」を主るといわれます。
「心」の読み方は「しん」です。所謂心臓の「心」ですね。心臓は現代医学でも中医学でも血液循環を行うポンプとしての働きがあると考えられています。しかし、中医学では「こころ」としての働きもあると考えています。夏の暑さは心臓に大きな負担をかけます。したがって働きすぎは控えて心を休ませてあげることが大切です。
【夏の養生】
甘い食べ物は「湿(しつ)」を生む原因となります。湿とはむくみや下痢の原因となる余分な水のことです。胃腸は湿に対して弱い臓腑ですので、甘いものを食べすぎて湿を生み胃腸が弱り、そして食欲不振となって夏バテが発生することにつながります。日本では古くから夏には麦茶を飲む習慣がありますね。実は麦茶は湿を抜くタイプのお茶なのです。常温以上の麦茶を飲むように心がけるとよいですよ。※ちなみにビールは湿を発生させる飲み物です。そして冷やして飲むので、胃腸が弱りさらに湿を発生させます。揚げ物も湿を発生させる食べ物です。なのでビールと素揚げの蛸は最強の不養生ということです。
前述のとおり甘いものは避けた方が良いのですが、その他の胃腸を弱らせる脂っこいもの、味の濃いものはなるべく避けるようにしましょう。そして毎日両手にモサッとのるくらいの葉物の野菜を食べ、そして血液をサラサラにして利尿を促すしいたけ、きくらげ、こんぶ、玉ねぎ、ニンニク、熱を発散させるゴーヤ、トマト、セロリ、スイカ、冬瓜などを多く食べましょう。特に熱を冷まし、利尿作用もあるスイカはおススメです。ただスイカは食べ過ぎるとお腹を壊す原因にもなるので注意しましょう。
熱には赤い食品、苦い食品などがよいです!
赤い食材:スイカ、あずき、レバー、トマト、リンゴ、イチゴ、うなぎ
苦い食品:ゴーヤ、さんま、緑茶、セロリ、パセリ、ミョウガ、紫蘇など
その他健康食品として板藍根、スベリヒユ、菊花、西洋人参などを摂取するとよいです。
睡眠を十分にとり、体力回復に努める。そしてストレスも発散するようにも努める。冷房の効かせすぎは体表の汗腺を閉じてしまい、暑い室外に出た時に熱を発散できなくなります。冷房が避けれない状況では衣服を一枚多く羽織る。夜はシャワーではなく湯船にしっかりつかり、心身ともにリフレッシュする。また平素から軽めの運動で体力を鍛える。軽めの運動は人によって異なるが、軽く汗をかくくらい運動であればよいでしょう。運動をする時間帯は朝晩の涼しい時間帯がおススメです!
【最後に】
要するに良く寝て、冷たいもの飲食しないようにして、冷房に注意して、あっさりした食べ物を中心に生活する、日ごろから私共が伝えてる普通の養生です。このブログまでたどり着いた方のほとんどは既知かと思います。しかし、皆様の周りの方々は養生のことを知っていまか?もし知らないようであれば、教えてあげましょう。ただあまりしつこく言うと怒られますので、程々にね(:D)┓ペコ
おしまい