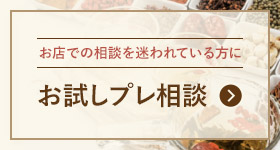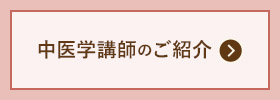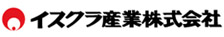雨水という言葉は、降雨が始まり雨量が多くなることを表しているだけでなく、気温が上昇して雪が解け、万物が芽生え始めることを表しています。 雨量の増加に伴い、湿気も多くなります。中医学では、湿邪は脾陽(消化器系)にダメージを与え、消化機能の低下をもたらします。そのため、雨水の前後は脾胃のケアに重点を置くのが大事です。飲食上は平性の食物が宜しく、性質が温和な甘味の食物を適量摂り、生物や油こい物は少量にと …
続きを読む季節のキーワード
- 日本の季節にあわせた、暮らしと漢方についてのコラム
二十四節気~雨水①
二十四節気~立春②
立春の養生 早春の時期は、睡眠は“遅寝早起き、日と共に起きる”の規則に従うべきです。意味は、人の生活リズムと日の出日の入りのリズムを合わせましょうということです。つまり“遅寝”といっても日の入りと共に寝るという意味です(笑) 睡眠時は頭を東側にし、睡眠前にお湯で足を洗い、両手で両足特に涌泉穴をマッサージすると、スムーズに入眠できます。 朝は先ず頭脳をクリアにするために、目を開け、次に目を閉じて両手 …
続きを読む二十四節気~立春①
立春は、一年の中で第一の節気であり、万物が復活する春が始まるサインです。 「一年の計は春にあり」、立春の日に春を迎えるのは既に3000年余りの歴史があり、多くの地方に『咬春』『尝春(春を味わう)』などの伝統的な食習慣があります。 中医では春は木に属し、肝と相応するので、飲食養生では春の陽気の初上昇、万物始まりの特徴に適応するべきであり、辛甘発散の品を食すべきで、酸収の味は食すべきではありません。 …
続きを読む二十四節気~大寒②
大寒は“蔵”を重視すべきである 人々はこの期間精神の安静を心がけ、神を体内に貯蔵し外に露出しないようにすることで、冬を安らかに越すことが出来るという意味です。冬の三か月人体の陽気は冬眠状態であり、この時期は早く寝て遅く起き、イライラして怒ることを避け、安易に陽気を乱さないようにしましょう。つい一昨日、薬局の窓際のデスクでこちらの原稿を書いていたら、この大寒の寒気で危うく風邪をひきそうになりました。 …
続きを読む二十四節気~大寒①
大寒は二十四節気中最後の節気で、『大寒を過ぎたら、ちょうど一年』などと言われます。大寒の日は、中国北方では『消寒糕』を食べ、南方では鶏スープを飲む食習慣が昔からあります。 大寒と立春は相交わっているので、飲食養生では滋養のある食べ物は少しずつ減らしていき、昇散作用のある食物を追加していくと宜しいです。 大寒の節気食材 乳鳩:生後一ヶ月以内の鳩のひな鳥を指します。鳩肉は味が美味しく、たんぱく質を豊富 …
続きを読む二十四節気~小寒
小寒は一年で最も寒い日にもうすぐ入るというサインです。今年、東京では小寒を待たずして、先週大雪が降り、マイナス0度を切りましたが(苦笑)。 中医学では寒は陰邪であり、人体の陽気を損傷しやすいと考えます。 この時期は温熱の食物を多食し、身体を補益し、耐寒能力を向上させるのが宜しいです。 小寒の節気食材 豚すね肉:前側と後ろ側に分類されますが、前側のすね肉は皮が厚く、腱が多く、コラーゲンが豊富で、赤身 …
続きを読む二十四節気~冬至②
前回に引き続き、冬至のお話です♡ 冬至は養陽が宜しい 冬至は二十四節気の中で最も早く定められた節気です。冬至の日は北半球で昼間が最も短く、夜が最も長くなります。 古代から『冬至一陽生』という説法があります。意味は冬至から陽気がゆっくりと回復して昇り始めるということです。 中国では古代から冬至を大変重視し、「冬至大如年(冬至は新年がごとし)」の説法があります。冬至に北部では餃子、南部では湯円(餡入り …
続きを読む二十四節気~冬至①
冬至は一年の中で陽気が初めて生まれる時であり、古代から養生修練では陽気が初めて生まれるこの時期を非常に重視しています。そのためこの冬至の養生は非常に重要です。 冬至は養陽が宜しい 冬至は養生学上、特に中高年以降の人々にとって最も重要な節気です。古代から“冬至一陽生”という言葉があり、陰気が冬至に達した時最も盛んになった後衰えはじめ、同時に陽気が芽生え始めます。古人は陽気が芽吹くこの時期の養生修練を …
続きを読む二十四節気~大雪②
前回は二十四節気の紹介と、大雪のこの時季にオススメの中医養生法三点と食材一点をご紹介しました。引き続き養生法四点とオススメ食材2点をご紹介します。 ④心を整える:冬は心が沈みがちになりやすい季節です。多くの疾患がメンタルの問題から引き起こされます。気分の落ち込みを変える最も良い方法は、体を動かすことで、ジョギングやダンス、スケート、野球など、どれも冬の気分の落ち込みを解消し、精神を保養する良薬です …
続きを読む二十四節気~大雪①
当店は、日本橋という花のお江戸の中心にありますが、薬局で四季の移ろいを感じるといったらおかしく思われるかもしれませんね。 しかしながら、春は花粉症、梅雨時は食欲不振、浮腫、湿疹、夏は夏バテ、秋は咳、喘息、肌や髪の乾燥といった具合に、いらしたお客様の症状によって薬局にいながらいつも季節の移り変わりを感じております。 中医学には「整体観念」という考え方があり、身体を一つの総合的な有機体として見る他、身 …
続きを読む