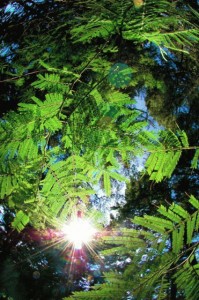やっと夏の暑さも一段落。朝晩は肌寒さも感じる秋の季節となりました。こんにちは。櫻井です。
秋になって疲れが取れない、だるい、元気が出ない、口や喉が渇く、手足がほてるといった症状がみられるかたも多くいらっしゃるのではないでしょうか。いわゆる「秋バテ」の状態です。
今年のような猛暑に限らず、夏はたくさん汗をかきます。そうすると体内の水分は消耗するので、おのずと水分を摂りたくなってしまいます。暑さが我慢できずどうしても冷たいものもとりがちになってしまいますね。そうすると湿気や冷えが苦手な内臓、とくに胃腸機能は低下しやすくなります。胃腸は口から入れたものを消化し、体に必要な物、いらないものに分けて、必要なものからエネルギーや血、潤いを造る場所です。ここが弱ってしまうと、不必要なものが溜まってしまい、さらに必要なエネルギーや血、潤いが作り出せなくなってしまいます。そこで秋になると前途の、疲れが取れない、元気が出ない、口や喉が渇く、手足がほてるなどと言った症状がでてきてしまうのです。これが『秋バテ』の正体です。
秋は乾燥の季節で、この乾燥に大きな影響を受けるのが「肺」です。″中医学で言うところの「肺」とは、鼻、喉、気管支、皮膚などを含めた広い意味での呼吸器系をさしていて、全身のエネルギーの働きを調節し、呼吸や水分代謝をコントロールし、さらに免疫機能の一部も担っているとされています。これからますます乾燥してくると、肺は乾燥の影響を受け、潤いが不足し、気道(肺に通じる空気の通り道)の抵抗力が落ち、カゼ、空咳、肺炎などの呼吸器のトラブル、ドライマウス、ドライアイ、声のかすれ、アレルギー疾患、肌の乾燥など様々な症状が現れやすくなる”と言われています。
秋バテ対策におすすめの食材はレンコン、梨、ブドウ、ユリ根、クコの実、豆乳、白米、はちみつ、落花生、杏仁豆腐、豚肉、すっぽん、カキ、カモ肉、なまこ、あわび、ハマグリ、白菜、冬瓜、胡麻、キクラゲなどがおすすめです。
中医学で秋は、夏の間に消耗したエネルギーを補い、冬に備えて体力を養い、身体を調節する期間。食生活や生活習慣を見直して、早めに改善して、心地よく秋をすごし、きたるべき冬に備えたいですね。