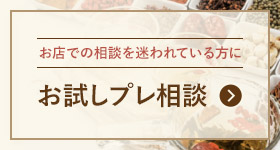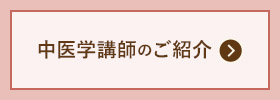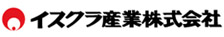夜に足がソワソワむずむずして眠れない、という症状に悩まされている方、
夜に足がソワソワむずむずして眠れない、という症状に悩まされている方、それは「むずむず脚症候群」かもしれません。
むずむず脚症候群について、西洋医学と中医学両方の観点から見ていきましょう。
むずむず脚症候群とは
むずむず脚症候群は、レストレスレッグス症候群(RLS)とも呼ばれます。
じっとしているときに、足に異常な感覚が生じ、動かさずにはいられなくなる病気です。
中年以降で起こることが多く、男性より女性に多い傾向があります。
この病気には4つの特徴があります。
①足を動かしたい衝動がある
②安静時に症状が出現、または悪化する
③夕方・夜間に症状が出現、または悪化する
④動かすことで改善する
主な症状は足に出現しますが、人によって体幹や腕、顔などにも出現します。
また、夕方から夜間にかけて症状が現れたり強くなったりするため、睡眠障害の原因となることがあります。
むずむず脚症候群の原因
むずむず脚症候群の原因は、主に神経伝達物質のドパミンなどが関与しているといわれていますが、まだ完全には解明されていません。また、以下のような要因がある方にも症状が見られることがあります。
・鉄欠乏性貧血
・糖尿病
・関節リウマチ
・パーキンソン病
・慢性腎不全(人工透析をしている方)
・妊娠中
病院での治療
病院での治療法としては、生活習慣の改善や薬物療法が一般的です。
●生活習慣の改善
・規則正しい生活
・適度な運動
・カフェインやアルコール、たばこを避けること
●薬物療法
・鉄剤(鉄欠乏性貧血がみられる場合)
・ドパミン作動薬
・ガバペンチンなど
中医学で考えるむずむず脚症候群
中医学では、むずむず脚症候群の症状について「肝腎陰虚」「気血不足」「瘀血」「痰湿」と関連していると考えられています。中医学の視点からのアプローチを紹介します。
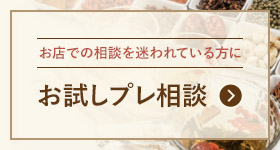
肝腎陰虚
「陰虚(いんきょ)」とは、体内を滋養し、潤している体液の不足のことです。
一般的に陰虚で起こる症状としては、ほてり、のぼせ、目や喉の渇き、肌の乾燥、五心煩熱(手のひら・足の裏が熱く感じる、気分がソワソワ・イライラする)などがあり、また、これらの症状は夕方以降に感じる、あるいは悪化する傾向があります。
陰虚は、生活習慣(食生活)、加齢、過労、久病(長期間の病)によって起こりやすくなります。
そして「肝腎陰虚(かんじんいんきょ)」は、五臓の「肝」と「腎」に「陰虚」がある状態です。
「肝」は筋肉や腱の健康を保つ役割が、「腎」は骨や髄の健康を保つ役割があります。
「肝腎」を潤し養っている体液の不足が、筋肉や神経系に影響を与え、症状の原因となっている可能性が考えられます。
「肝腎陰虚」がある方には、不足している体液を補うような漢方薬を用います。
肝腎陰虚の方の養生:
・辛味の強い食べ物は摂りすぎないようにする
・甘味と酸味のある果物を摂る
(「酸甘化陰」といって、甘味と酸味の両方があるものは体液を増やすといわれます)
・汗をかきすぎないように気を付ける(炎天下の野外での作業、長風呂、サウナなど)
気血不足
「気血不足(きけつぶそく)」は、身体や内臓を動かすエネルギーである「気」と、潤いや栄養を届ける「血」がどちらも不足している状態です。
偏った食事や消化器系の不調による気血の生成不足や、過労などによって気血の消費量が多いと起こりやすくなります。
しなやかな筋肉の健康には、十分な「血」が必要です。
また「気」は、物質である「血」を動かし、身体の端々に届けます。
「気血不足」の状態であると、必要な場所へ「血」が届きづらくなります。
「気血不足」がある方には、不足している気血を補う漢方薬を用います。
気血不足の方の養生:
・過労に気を付ける、疲れるまで作業をやらない
・消化しやすく、バランスのよい食事を摂る
血瘀
「血瘀(けつお)」は血流が悪く、滞っている状態を指します。
一般的に「血瘀」である方は、皮膚のがさつきや、痛み、こり、血色が暗い、舌の裏側の静脈が張っているということがあります。
「血瘀」は体質によるもののほかに、別な要因から起こることもあります。
よい血流を保つ気血の不足や、動脈硬化などによる血管のしなやかさの悪化、ストレスによる筋緊張の影響などが、その原因として挙げられます。
そのため、「血瘀」の方には、血流を良くする漢方薬のほか、「血瘀」に体質が傾いてしまった要因に合わせて漢方薬を用います。
血瘀の方の養生:
・気を巡らせる香りのよい食材や、血流によい食材を選ぶ
・適度に運動を行う
痰湿
「痰湿(たんしつ)」とは、「脾胃(ひい:消化器系)」の働きが悪くなり、そこから体内の水液代謝や循環が悪化して、老廃物がたまっている状態です。「痰湿」は「気血」の流れを悪くさせ、それによって「気血」が必要な場所へ届きにくくなります。
そのため「痰湿」がある方には、胃腸をととのえながら、体内の「痰湿」を取りのぞきやすくするような漢方を用います。
痰湿の方の養生:
・まず胃腸のケアを
・消化が良く、あっさりした食事を心がける
・適度に運動を行う
※実際の相談では、それぞれの体質ひとつだけではなく、複数の要因が絡み合っていることが多くあります。
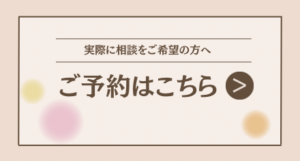
むずむず脚症候群でお悩みの方へ
以上、むずむず脚症候群の主な原因、治療、中医学からの視点をご紹介しました。
むずむず脚症候群には別の病気が隠れている場合もあるため、病気が疑われる場合はまず専門医に相談し、隠れた病気がないかを確認しましょう。その上で、漢方薬による症状の緩和や、根本的な体質改善を行うことをおすすめします。
むずむず脚症候群でお困りの方、どうぞイスクラ薬局にもお気軽にご相談ください。
まずはメール相談をご希望でしたらお試しプレ相談、
ご予約でしたらお電話もしくはご予約フォームから承ります。
快眠、快調な日々を目指して、お力添えいたします。
参考資料:「e-ヘルスネット(厚生労働省)」、「神経治療 Vol.38 No.4 」、日経DI