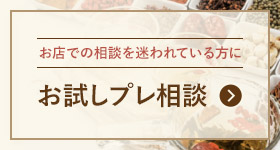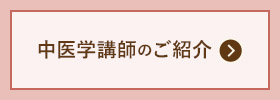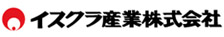「生理の前になると、微熱っぽくなるのがつらい…」
「生理中に37℃近い体温が続いているけど、これって異常なの?」
「熱があるのに風邪じゃない。毎月この症状があるってことは、ホルモンのせい?」
このように、病気というほどではないけれど、「なんとなく熱っぽい」「だるい」「頭が重い」などの体調不良が、毎月決まって生理のタイミングで起こるという女性は少なくありません。
この記事では、女性ホルモンの働きと生理周期の変化、そして中医学の視点から、生理前後の「熱っぽさ」や「微熱」の原因について詳しく解説します。

女性ホルモンの特徴と生理周期
月経周期は、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンによってコントロールされています。主にこの2つのホルモンにより、女性の体のリズムは動きます。
エストロゲンの特徴
エストロゲンは、第二次性徴とともに増える女性ホルモンです。・女性らしい身体をつくる
・自律神経、感情、骨、皮膚、内臓などと大きく関わっている
・妊娠準備のため子宮内膜を厚くする
・分泌の多い時期は心身安定し体調が良くなる
などの特徴があります。
プロゲステロンの特徴
プロゲステロンは、妊娠のために体を整えるホルモンです。・受精卵が着床しやすい環境をつくり、妊娠が成立したときは維持させる
・体内の水分保持や食欲を増進させる
・基礎体温を上昇させる
・分泌の多い黄体期には頭痛、イライラ、不安感、不眠、むくみ、乳房の張りなどの症状が出やすい
などの特徴があります。黄体期(生理前)に出る頭痛、イライラ、不安感、不眠、むくみ、乳房の張りなどの症状がひどくなり不調を感じると、月経前症候群(PMS、または生理前症候群)と呼ばれます。
ホルモンによる生理周期と体温の変化
月経周期は大きく以下の4つに分かれます。卵胞期(生理後〜排卵まで)
脳から分泌されるFSH(卵胞刺激ホルモン)により卵胞が育ち、エストロゲンが徐々に増加。子宮内膜が厚くなっていきます。この時期は体調が比較的安定し、心も軽やかに感じやすい時期です。排卵期(中間期)
エストロゲンの急増により、LH(黄体化ホルモン)が分泌され、排卵が起こります。排卵日前後にはホルモンバランスの変化から、体調に揺らぎが出やすくなります。黄体期(排卵後〜次の生理まで)
排卵後の卵胞は黄体に変化し、プロゲステロンを分泌。このホルモンは基礎体温を0.3〜0.5℃ほど上昇させます。これが、黄体期=高温期と呼ばれるゆえんです。プロゲステロンの影響で、体に水分がたまりやすくなったり、気分が落ち込んだり、イライラ、不眠などPMS(月経前症候群)につながることも。月経期(生理期間)
妊娠が成立しない場合、ホルモン分泌が急激に低下し、子宮内膜が剥がれ落ちて月経となります。月経中はエストロゲン・プロゲステロンの両方が低下し、ホルモンの谷間に入るため、身体のエネルギーやバランスが不安定になりやすくなります。このように、月経周期にともない体温も上下します。とくに黄体期から生理中は高温状態が続くため、微熱を感じやすいのは当然とも言えるのです。
生理中の発熱はなぜ起こる?
月経中の発熱は、感染症などによる発熱とは原因が異なります。月経前後に体調を崩す人は、もともとの体質が大きく関係しています。中医学から考える生理中の発熱のメカニズム、生理で調子を崩しやすい代表的な体質4タイプについて解説します。中医学から見る「生理中の発熱」
中医学では「気・血・津液(しんえき・体の潤い栄養)」のバランスが崩れることでさまざまな症状が生じると考えます。「発熱」は、外からのウイルスによるものだけでなく、体内から生まれる“内熱(ないねつ)”が原因で起こることもあります。特に月経に関連した発熱は、「気・血」そして「陰陽」のバランスが崩れた結果と考え、以下の4つの体質に分けて考えます。
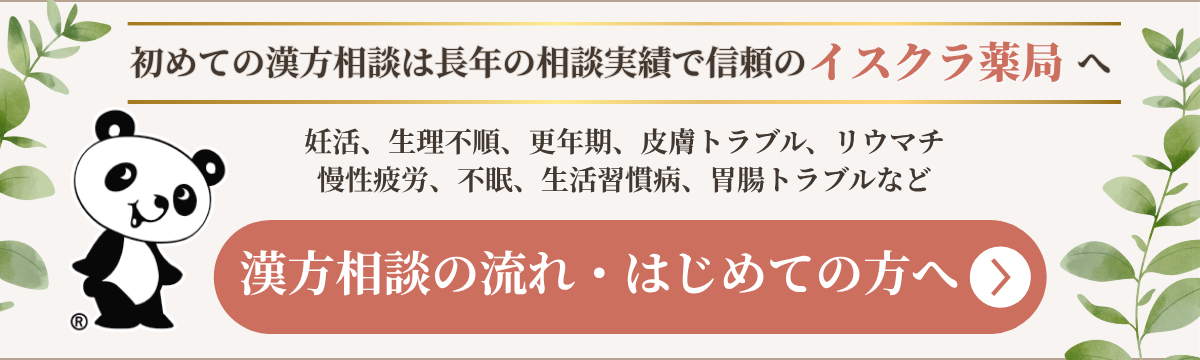
生理前後の発熱の原因を体質別に解説
肝鬱化火(かんうつかか)タイプ
【症状】
・生理前あるいは生理時に微熱が生じ、生理が終わる頃には下がる
・生理周期が短くなる
・経血が濃く鮮紅色
・乳房が張る
・口が渇く
・便秘気味
・イライラ、怒りやすい
・舌色が赤色
・黄体期の基礎体温高め、月経前症候群(PMS)の症状が多い
・基礎体温は安定せず波状になる
【原因・特徴】
中医学では、ストレスは肝(五臓六腑のうち、血を蔵するとされるもの。肝臓そのものだけを指すのではない)の働きに大きく影響すると考えます。ストレスで肝のうっ滞が起きると、気滞と呼ばれる状態(気の巡りが悪く内臓や器官などの動きに支障が出る)になります。更にストレスが高じると、肝から熱が生じ、火と化すとも考えられます。
肝うつ化火型の生理前後の発熱は、
・ストレスが多く肝うつ気滞が続くと化火し、火熱が生じたために発熱する
ことが原因と考えます。
また、特徴として、
・生理が終わる頃にはスッと楽になる
ことが挙げられます。
よく使われる漢方薬
イスクラ逍遥顆粒(しょうようかりゅう)、加味逍遥散(かみしょうようさん)、イスクラ頂調顆粒(ちょうちょうかりゅう)など

瘀血内阻(おけつないそ)タイプ
【症状】
・生理前あるいは生理時に微熱が生じる
・ひどい腹痛
・経血の色は暗紅で塊が多い
・舌は紫色、斑点がある
・鎮痛剤を服用しないと我慢できない痛み
【原因・特徴】
瘀血内阻タイプは、各種の原因で血の巡りが悪くなっているために引き起こされる体質です。中医学では、血の巡りが悪い状態が続くと、血から熱が生じて発熱すると考えます。
おけつ内阻型の生理前後の発熱は、
・血流が滞り、血が子宮に停滞し次第に化熱し、生理時に「瘀熱(おねつ)」がピークになり発熱する
ことが原因と考えます。また、特徴として、
・生理終了後には熱も下がる
ことが挙げられます。
子宮内膜症との関連も強く、子宮内膜症の約20%の方が生理時の発熱を経験しているとの報告もあります。子宮内膜症はひどい月経痛を伴い、瘀血内阻型の傾向にあります。
よく使われる漢方薬
血府逐瘀丸(けっぷちくおがん)、桃核承気湯(とうかくじょうきとう)、温清飲(うんせいいん)、芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん)など

気血両虚(きけつりょうきょ)タイプ
【症状】
・生理中あるいは生理後に微熱が生じる
・経血が淡色で量が多い
・冷え
・めまい
・気力がない、倦怠感
【原因】
気血両虚タイプとは、体を動かしたり温めたりするエネルギー(気)も、体のすみずみまで栄養分やホルモンを運ぶ血も不足している状態のことを指します。気が足りないので体が冷えやすく、気力が出ず、だるくなりがちです。また、血分が足りないので、経血の色が淡くなります。中医学では、気が血をコントロールしていると考えますが、気血両虚タイプは気が不足しているので血のコントロールができず出血しやすく、経血の量が多くなると考えます。
気血両虚タイプの生理前後の発熱は、
・気血の消耗や脾虚(消化器官の弱りによる消化吸収機能の不足)によって元々気血が作られにくい体質
・生理の出血によってさらに気血が流出し不足するため体表の寒熱のバランスが崩れ、発熱する
と考えられます。
よく使われる漢方薬
イスクラ婦宝当帰膠B(ふほうとうきこうびー)、イスクラ心脾顆粒(しんぴかりゅう)など
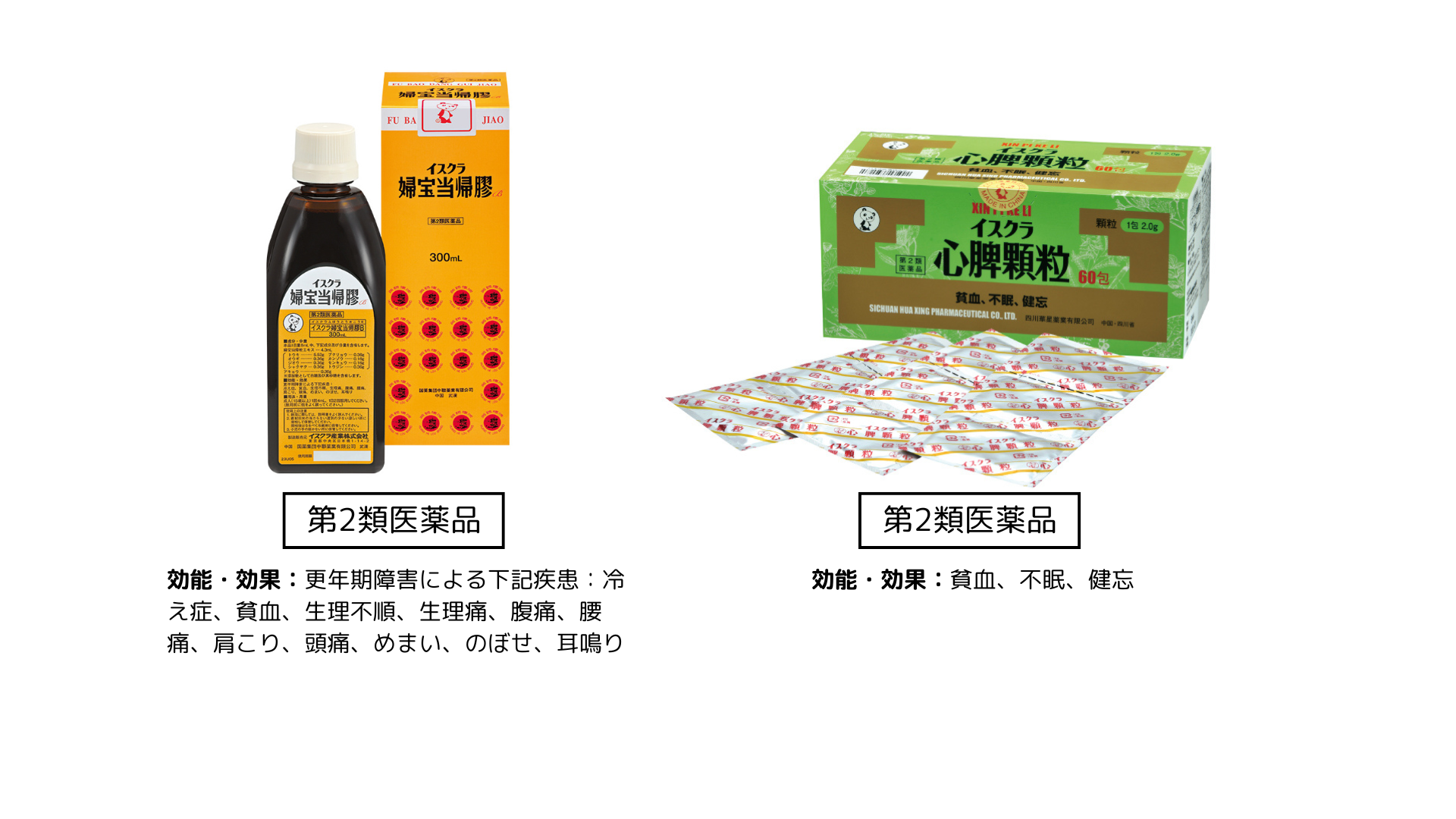
陰虚火旺(いんきょかおう)タイプ
【症状】
・普段から微熱があり生理時に熱が高くなる
・特に午後になると発熱する
・経血が暗紅色で少量
・両頬がポッと赤い
・手のひら、足の裏のほてり
・口の渇き
【原因】
中医学では、熱を冷ましたり体を潤したりするものを、陰陽のカテゴリーでは陰に分類します。陰が不足(陰虚)すると、ヤカンの水が少ないとすぐ沸騰するように熱が生じると考えます。
陰虚火旺型の生理前後の発熱は、
・経血が排出されたことで陰血が消耗
・身体の陰不足により陰陽のバランスが崩れ発熱する
ことが原因として考えられます。
よく使われる漢方薬
イスクラ瀉火補腎丸(しゃかほじんがん)、イスクラ杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)、二至丸(にしがん)など

風邪や感染症との鑑別が重要
月経中に発熱があったとしても、すべてがホルモンや体質に起因するとは限りません。以下のような場合は感染症など他の病気の可能性も考え、慎重に見極める必要があります。以下のような場合は、婦人科や内科を受診しましょう。安易に自己判断せず、必要に応じて医療機関を受診することも大切です。
・高熱(38.5℃以上)が続く
・のどの痛み、咳、鼻水など風邪様症状がある
・排尿時の痛み、頻尿、血尿がある(膀胱炎など)
・下腹部の激しい痛み、吐き気、嘔吐(子宮や卵巣の感染症など)
・白帯(おりもの)の量や色、臭いに異常がある(膣炎や子宮内膜炎の可能性)
・日常生活に支障があるほどの倦怠感や頭痛、腹痛
・基礎体温が乱高下している、あるいはいつもと明らかに違う
・市販薬やセルフケアで改善が見られない
・妊娠の可能性がある
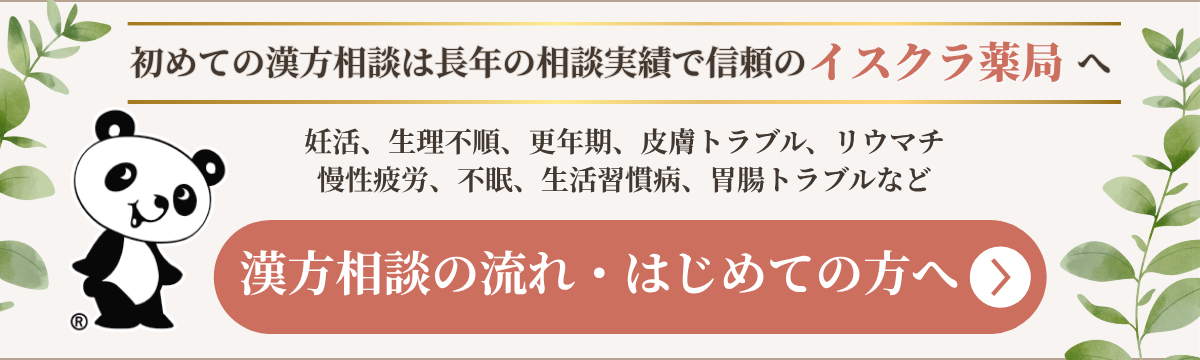
基礎体温の記録と観察の重要性
月経周期に伴う体調の変化を把握するうえで、「基礎体温表」は非常に有効なツールです。基礎体温は、排卵の有無、ホルモンバランス、体質の傾向などを知る手がかりとなります。
中医学においても、基礎体温の波形は、気血のバランスや陰陽の状態、冷えや熱の傾向などを知る手段として活用されています。
基礎体温からわかること
・排卵の有無(2層性になっているか)・高温期と低温期の差(0.3~0.5℃の変化)
・高温期の持続期間(約12〜14日が理想)
・生理開始直前の急激な体温低下
・全体的な体温の高さや安定度
発熱があった際にも、通常記録している基礎体温表を確認することで、月経周期に伴う自然な変動か、それとも感染症などによる異常な発熱かを判断できます。また、PMSや不妊などの診断にも役立ちますので、日々の観察がとても大切です。
発熱時の対処法
生理前後の発熱に対しては、無理せず休息をとることが基本です。以下のような生活習慣やセルフケアを心がけましょう。
日常生活でできること
・冷え対策を徹底する: 下腹部や足元を温め、冷たい飲食物は避ける。(主に瘀血、気血両虚タイプに有効)・十分な睡眠をとる: 夜更かしや睡眠不足は肝の機能を低下させ、気血の生成を妨げます。
・軽い運動やストレッチ: 気血の巡りを良くし、瘀血を防ぐ。
・バランスの良い食事: 気血を補う黒豆、なつめ、鶏肉、小松菜、山芋などがおすすめ。
・ストレスケア: ハーブティーや深呼吸、アロマなどでリラックスを。
病気ではないけれど・・・毎月の「不調」に向き合う
生理中の発熱が毎月続くと、病気ではないとわかっていても不安になりますよね。実際、Q&Aサイトでは以下のような声が寄せられています。
「生理中、微熱っぽいのに風邪じゃない。熱が37℃台なのに、病院では異常なしと言われました。毎月これが続くのがしんどいです。」
「生理前に必ず体温が高くなって、頭がぼーっとするのが嫌です。」
こうした声は、まさに今回ご紹介した「内熱」や「ホルモンバランス」の影響によるものと考えられます。
病院での治療はホルモン剤の使用などになりますが、体質改善のために漢方薬を服用することもひとつの方法でしょう。
漢方で“内側から”整える選択肢も
西洋医学では、生理にともなう微熱に対して明確な治療法がない場合も多く、「様子を見ましょう」で終わってしまうこともあります。そんなとき、中医学的な体質チェックを通じて、自分に合った漢方薬で体質を改善していくことは、大きな助けとなるでしょう。
生理の発熱にお悩みで、漢方の服用に興味がある方はイスクラ薬局にご相談ください。イスクラ薬局では、漢方に関する専門的な知識を持つスタッフが、身体の状態や体質に合わせた的確なアドバイスをしております。
初めての方でも安心して相談できるよう、メールでのお試しプレ相談や、お電話もしくはご予約フォームを通じたご相談も承っています。生理の発熱を解消し、快適な生活を取り戻すために、ぜひイスクラ薬局にご相談ください。
都内に4店舗イスクラ薬局直営店はコチラから
お近くの漢方専門店はコチラから
オンラインで体質チェック!お試しプレ相談
関連リンク 合わせて読みたい
月経から判断できる体質チェック1
月経から判断できる体質チェック2
ギザギザしているのはストレス状態?中医学から見た基礎体温のお話
婦宝当帰膠ってすごい!
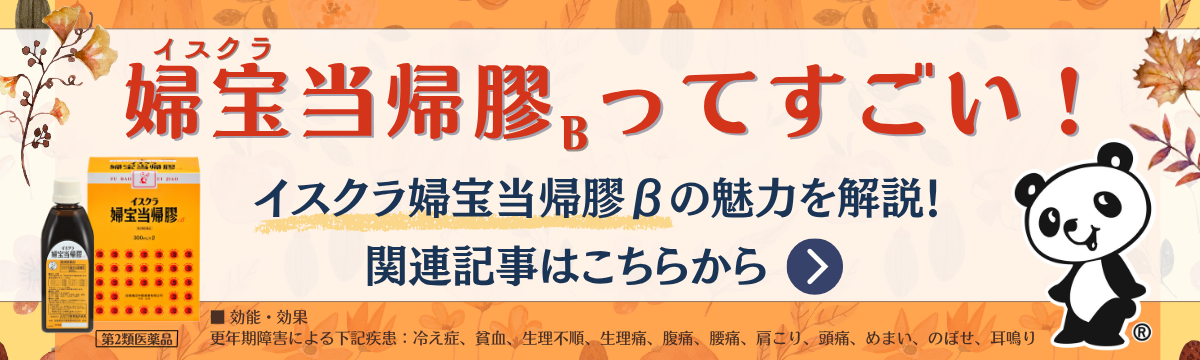
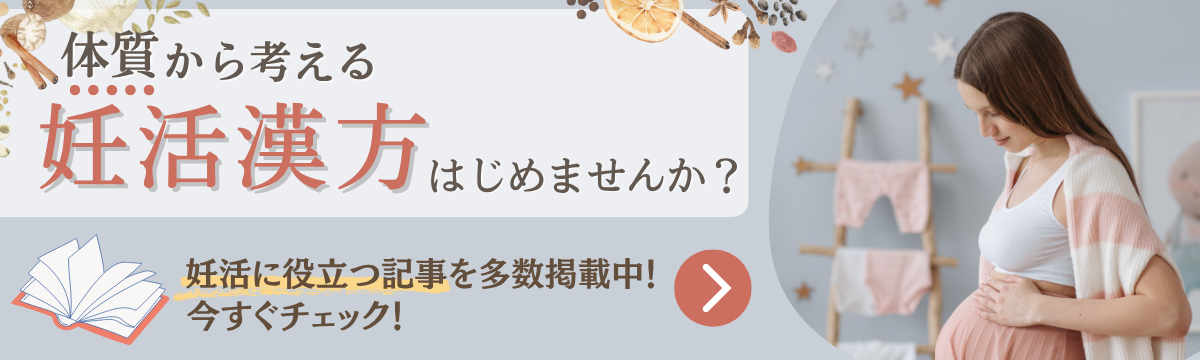
生理,発熱,